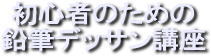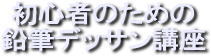
<携帯版>
豊中美術研究所
デッサン講座
INDEX
←BACK
NEXT→

NO.197
03/01/24
こんにちは
時計屋
今回はかなり拡大できるようにしました。
モチーフ:計量カップ(アルミ)
ゴマをする棒
熱いナベを持つときの手袋
制作時間:10時間
用紙ですが、入試はケント紙が多いのですか?
モチーフは質感の違うものを3つ選んでみました。
カップのふち(向こう側)にハイライトがあったので、
ねりけしで消しましたが遠くから見るとへこんで見えてしまいます。
3Bくらいの鉛筆でかたちが、そう見えるように描いた方が良いのですか?
NO.198
03/01/24
Re: こんにちは
Hima@豊中美研
時計屋さん、
前回のよりずっとよく描けていますね。計量カップの金属の質感よく表現できています。ここまで独学で身につけられているとは驚きです。
構図について、それからそれぞれをもう少し大きめに描くことについて、これからは注意してください。
このスケッチブックは凹凸のある水彩画用のものではないですか?
最初のうちはケント紙で描くと(塗りこまずに線で描くことの)勉強になると思います。
柔らかい材質のもの「手袋」はともかく、今回も「すりこぎ」はもう少しメリハリをつけて硬さを表現すればよかったですね。
計量カップの側面がへこんで見えるのは垂直方向であるべき直線(いちばん明るいところの形)が微妙に曲がっているからでしょう。
カップの底辺と棒の先がわずかなりとも重なっているのは双方の表現にとってメリットはありません。
(離して描いても何の問題もないわけですから)
>3Bくらいの鉛筆でかたちが、そう見えるように描いた方が良いのですか?
受験生には基本的にはHBから2Bまででほとんどを描くように指導しています。それでは表現できないという必然性を感じてからより柔らかい(硬い)鉛筆を自覚して使うようにすべきだからです。
「見えるように描く」という配慮はもう少しあってもいいですね。
NO.199
03/01/24
Re: こんにちは
時計屋
一応、高校の美術の先生に見せているのですが、
「ここはどう描いたらいいですか?」と聞いても、
「そんなのいちいち言ってたら、モチーフが変わるたびに、描き方を言わなあかんやろ。」
てな感じで、とりあえず描いて自分で考えろ。みたいな先生で、
僕は基本的な知識がないので、かなり不安です。
けど、悪いところを言ってくれるので、直すべき点は微妙にわかったりします。
ということで独学ではないです。
それとケント紙のことですが先生に相談してみます。
勝手にかえると何か言われそうな気がするので・・・
>それからそれぞれをもう少し大きめに描くことについて
今は実物の大きさで描いてるのですが、実物よりも大きくなってもいいのですか?
>今回も「すりこぎ」はもう少しメリハリをつけて硬さを表現すればよかったですね。
硬さをだすにはどうすればいいのですか?
ハイライトをくっきりとだす、とかですか?
>受験生には基本的にはHBから2Bまででほとんどを描くように指導しています。
そうなんですか!?
僕は3H〜3Bまで使ってしまってます。
カップの手前にうっすらと影が落ちていました。
理屈で考えても理解できません。
こんな不思議な影も描くべきなのでしょうか?
それとも、普通こんな風に影ができるものなんでしょうか?
NO.200
03/01/25
Re: こんにちは
Hima@豊中美研
基本的には間違った指導はないようですので、高校の先生を信頼して頑張ってください。
描く前に「どう描いたらいいですか?」というのは、私の場合も困ってしまう質問で、たとえば「こうやってみましたが」とか「どちらがいいですか?」のほうがずっと答えやすいのです。
描く大きさは実物の1.2〜1.3倍くらいが適当です。一回り大きく描きます。
入試のデッサンは手に持って仔細にチェックされるのではなく、2〜3メートル離れて眺めて採点されると考えてください。(離れて見れば実寸大では小さく見えるでしょう?)
細かい部分にこだわらずに元気よく描いたほうがいいとよく言われるのもこのためです。
「すりこぎ」の硬さの表現は明部ではなく最暗部の強調でやってみてください。
明部・中間調部は質感(色や木目なども)の表現が主体になりますね。
カップの手前の影というのは実物を見ないのでよくわかりませんが、描く場所によって(部屋の照明によって)複数の影がでた場合に必要な影だけをピックアップして他は無視して描かないというのはよくやることです。
用紙と鉛筆の件は直接指導いただいている先生の判断に従ってください。
なお、スケッチブックでは描きながらの「紙の取りまわし」ができませんので、なるべく早めにカルトン+紙の組み合わせに切り替えられるほうがいいです。
NO.201
03/01/25
Re: こんにちは
時計屋
>入試のデッサンは手に持って仔細にチェックされるのではなく、2〜3メートル離れて眺めて採点されると考えてください。
大芸の入試は鉛筆精密描写となっておりますが、
その場合も、離れた場所からだけで採点するのですか?
>場所によって(部屋の照明によって)複数の影がでた場合に必要な影だけをピックアップして他は無視して描かないというのはよくやることです。
入試の時の部屋は普通の教室ですよね?
天井に蛍光灯がたくさんあるのを想像しますが、
入試の時も影を1つにするのですか?
NO.204
03/01/26
Re: こんにちは
Hima@豊中美研
時計屋さん、
>大芸の入試は鉛筆精密描写となっておりますが、
>その場合も、離れた場所からだけで採点するのですか?
もちろん大学によって(採点者によって)いろいろあると思いますが、基本的にはそう考えてください。
同じモチーフを描いたデッサンがズラーっとたくさん並ぶわけです。
その中でちゃんと訴えるもの(前に出てくるもの)がなければ、手にとって眺めて見てもらえない(細かいところまで見てもらえない)ということです。もちろん、細部も大切ですが。
薄いデッサン、弱いデッサン、小さいデッサン、元気のないデッサン・・・などは、ほとんど力の違わない人たちの作品を比較する場面では致命的な欠点になります。
>入試の時の部屋は普通の教室ですよね?
>天井に蛍光灯がたくさんあるのを想像しますが、
>入試の時も影を1つにするのですか?
画家は静物画を描くときに、モチーフにあたる光の具合にとても気をつかい最も適切な環境(光)のもとで描きます。作品の出来に大きく関係するからです。
入試の時、窓際のちょうど良い光線のあたる席に座った人が有利になるというのは不公平でしょう?
デッサンには蛍光灯がたくさんあることよりも優先して表現せねばならないことがいくらでもあります。
NO.207
03/01/26
Re: こんにちは
時計屋
>デッサンには蛍光灯がたくさんあることよりも優先して表現せねばならないことがいくらでもあります。
窓際に座れということですか?
結局、影は1つにしたらいいんですよね?
何回もすみません。
NO.208
03/01/26
Re: こんにちは
Hima@豊中美研
入試の時は好きな席を選べるわけではありません。
光線の具合が最悪の席だったからといって、採点時に下駄を履かせてもらえないのです。
目の前にあるモチーフをどのように表現するか、影を整理するものその工夫のひとつですね。
NO.209
03/01/26
Re: こんにちは
時計屋
じゃあ、どんな状態でも描けるようにならないといけませんね。
ありがとうございました。
←BACK
NEXT→
INDEX
<PC版>
豊中美術研究所